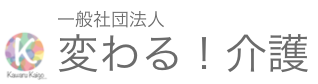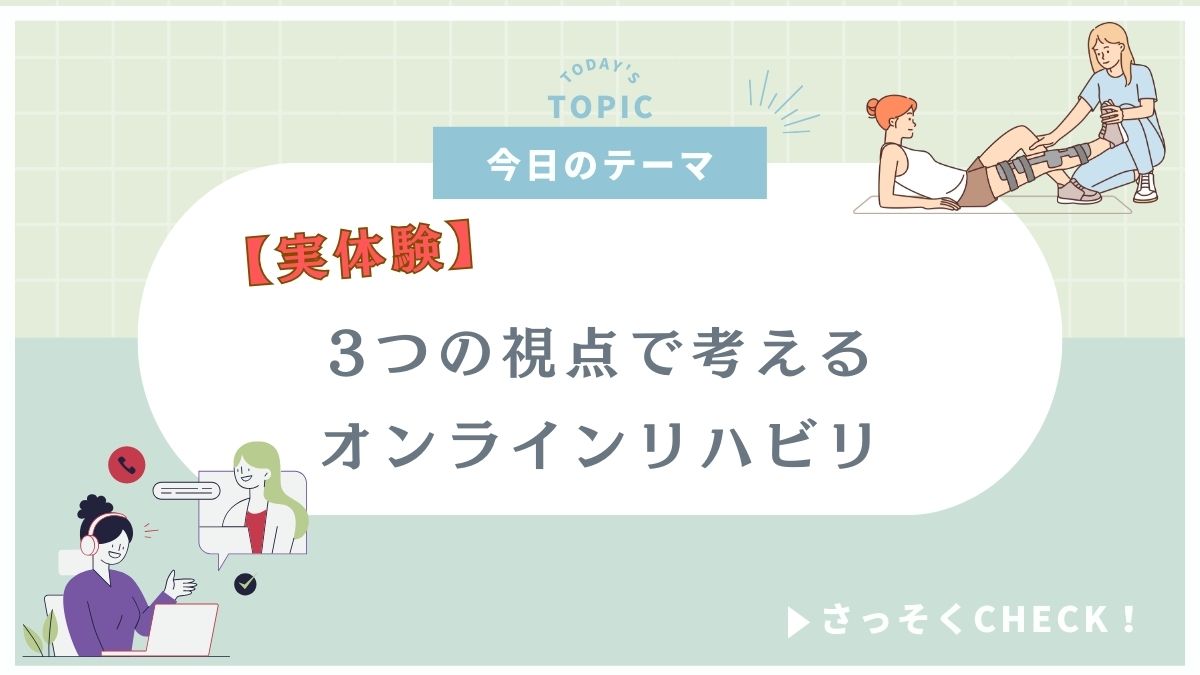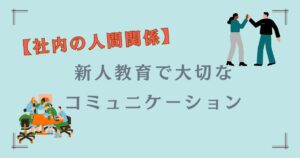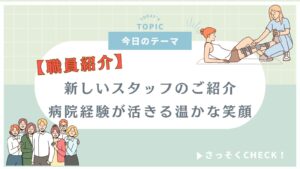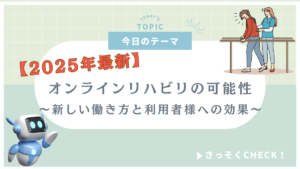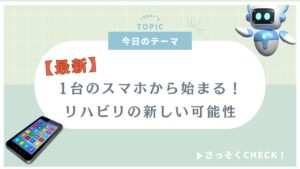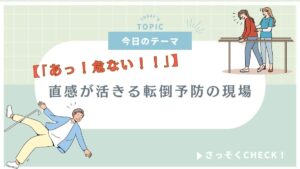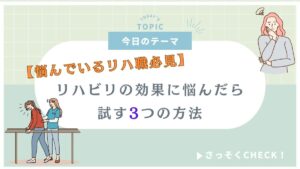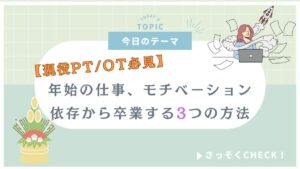みなさんこんにちは!
変わる介護の岩崎です。
今日は、変わる介護が新たに挑戦する
オンラインリハビリについて、
その可能性をお話ししたいと思います。
▼なぜ今、オンラインリハビリなのか
2019年の統計データによると、
日本のリハビリ職の約66.5%が医療施設に
所属していました(119,525人中79,502人)。
一方で、老人福祉施設での従事者は
約8.7%(10,356人)という状況でした。
この統計から少し時間は経っていますが、
リハビリ職の多くが医療施設に集中している傾向は、
現在も大きくは変わっていないのではないかと考えています。
そんな中、変わる介護に一つの相談が寄せられました。
「オンラインでリハビリはできないか」
この相談は、もしかすると医療施設以外の場所での
リハビリニーズが存在する可能性を
示唆しているのかもしれません。
そこで私たちは、
オンラインリハビリという
新しい可能性を探ることにしました。
今日はオンラインでリハビリを
実施するということについて考えてみました。
▼3つの視点の可能性
1. 利用者視点
画面越しではありますが、
利用者にとってはリハビリ専門職と
一緒に運動することで、
日々の活動に変化をもたらすことが
できるかもしれません。
移動の負担なく専門職の指導が受けられることで、
これまで継続的な運動が難しかった方々にも、
新たな選択肢を提供できる可能性があります。
また、複数の施設をつないで実施することで、
離れた場所にいる利用者同士の
交流の機会を作ることもできるかもしれません。
2. 施設視点
オンラインリハビリには、
柔軟な活用の可能性があります。
例えば必要な時に、
必要な分だけ依頼できるという視点です。
コストを抑えながら、
サービスの質を向上させる
選択肢として期待できます。
施設スタッフの方々の
負担軽減にもつながるかもしれません。
リハビリ職との連携により、
より効果的な支援の方法を
見出せる可能性もあります。
私たちリハビリ職の働き方の可能性を
広げられるチャンスにつながると感じたのは、
利用者様のメリットだけでなく、
施設側にもメリットを
感じてもらえると思ったからです。
3. リハビリ提供者視点
移動時間の削減により、
より効率的なサービス提供が
可能になるかもしれません。
例えば岩崎は都内ではなく、
埼玉の中でも山に近い所に住んでいます。
都心部まで通うには片道1時間以上かかります。
そのような遠方に住む
リハビリ職の新しい働き方の
選択肢になると感じています。
特に、これまで施設への直接訪問が
難しかった地域でも、
オンラインであれば
サービス提供が可能になります。
▼具体的な試行内容
今月から、以下のような形で試験的に実施していきます
・変わる介護の事務所と施設をオンラインで接続
・モニターやロボットを使用した双方向でのやり取り
・施設スタッフとの連携による安全確保
まずは集団体操を中心に、
どんな可能性があるのか、
実践を通じて探っていきます。
特に注意を払うのは、
安全面です。
オンラインという特性上、
直接的な介助ができないため、
施設スタッフとの綿密な連携が
不可欠となります。
また、画面越しでも分かりやすい
指導方法の確立も重要な課題です。
これらの点について、
試行錯誤しながら最適な方法を
見出していきたいと考えています。
▼今後に向けて
この1-2ヶ月の試行期間で、
以下の点を特に見極めていきたいと考えています。
・利用者様の反応と効果
・実施上の技術的課題
・安全面での具体的な配慮事項
・より効果的な実施方法の検討
・施設スタッフとの連携方法
まだ始まったばかりの挑戦です。
これからどんな可能性が
見えてくるのか
私自身もわくわくしています。
医療施設での経験を活かしながら、
新しい形でのリハビリテーションに
挑戦してみたいと考えている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方々と一緒に、
リハビリテーションの新しい
可能性を探っていけたら嬉しいです。
興味を持っていただけた方は、
ぜひ変わる介護までご連絡ください。
それではまた!
参考文献
理学療法士の統計データ(2019年)
https://rigakulab.jp/2019/12/19/id000023/