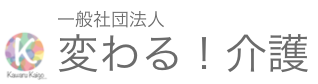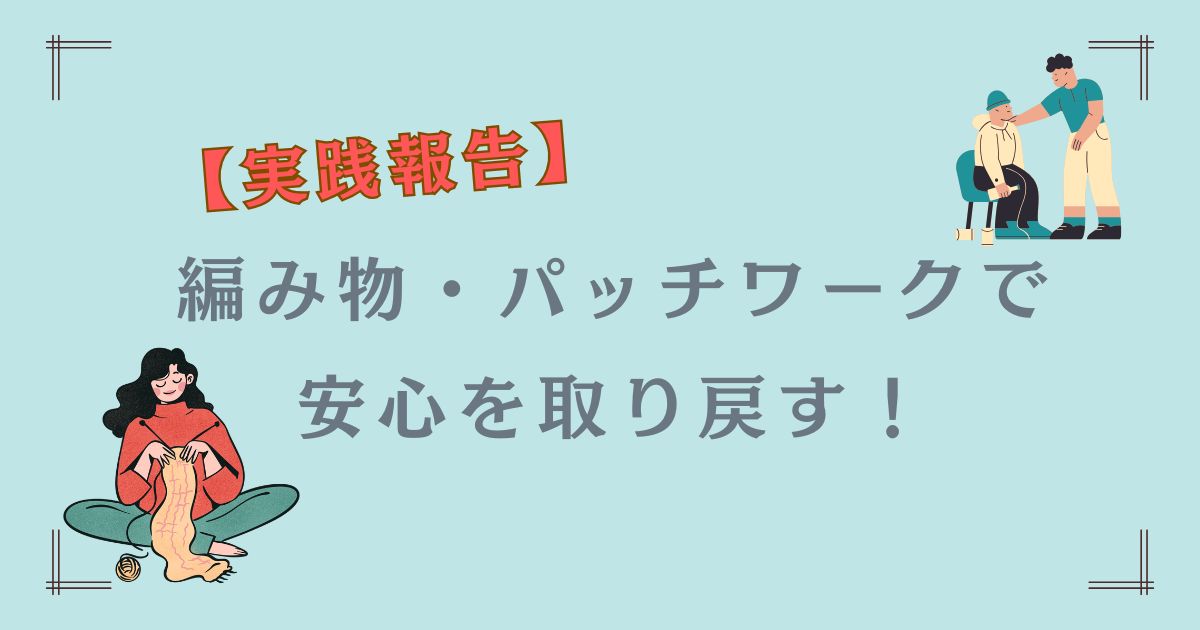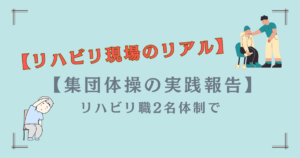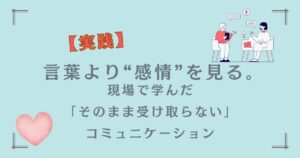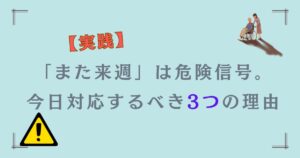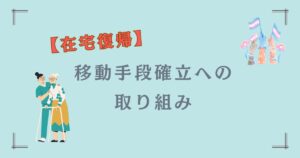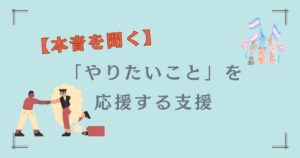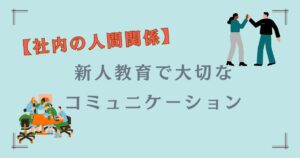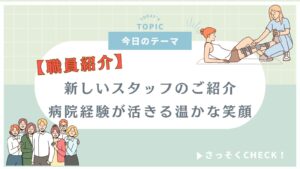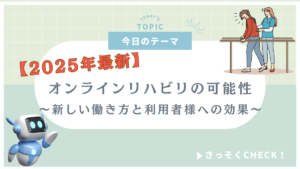みなさんこんにちは!
変わる介護の岩崎です。
今日のテーマは
【編み物・パッチワークを活用したリハビリの実践報告】
です。
最近、同僚のOTさんが利用者様に
編み物やパッチワークなどの作業活動を導入し、
利用者様の素敵な一面を引き出しています。
ポイントは「教わる」から
「教える」立場への転換です。
・認知症の方のリハビリに悩んでいる
・作業活動の具体的な導入方法が知りたい
・利用者様の役割づくりに興味がある
そんな方におすすめの内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
▼利用者様の状況
今回お話しする利用者様は
こんな方です。
・もともとパッチワークが得意
・膝の痛みがある
・認知症の診断あり
・夕方や一人になると「帰りたい」と不安げな様子
これまでの変化
この方は入居当初、
膝の痛みで歩くことが困難でした。
しかし、膝のサポーターを使用したり、
歩行機会を増やしたことで
手引き歩行ができるようになりました。
そして、現在は歩行器を使用し
お一人での移動が痛み無く、
実施できています。
しかし、運動能力が上がったことで、
新たな課題が見えてきました。
▼新たな課題
身体機能が改善した一方で、
認知症と思われる行動・心理症状が
目立つようになってきました。
特に夕方になると、
「家に帰りたい」と訴えられ、
落ち着かない様子。
この状況を見て考えたのが、
「安心して過ごせる方法はないか?」
ということで、
そこで思い出したのが、
お部屋に飾ってある
パッチワークの作品です。
利用者様が過去に作られた
「パッチワーク」の作品を見ながら
「一緒にやりませんか」と声をかけました。
▼作業活動の導入:編み物・パッチワーク
利用者様へのリハビリは週2回提供していたので、
チームで話し合い、落ち着いて
夕方を過ごせるようになることを
目的にパッチワークや編み物を試しました。
最初は失敗体験として
印象に残らないように努め、
作業に集中できることを目標にしました。
続けていく内に徐々に
利用者様主導で行えるようになった為、
「どうやったらいいですか?」
と質問をしていきました。
▼「教わる」から「教える」への転換
何回か一緒に編み物を行っている内に、
利用者様の方から
「ここはこうですね」
と教えてくださるようになり、
表情が変わりました。
利用者様が
「教える立場」
になることで
以下のような変化が生じました。
・笑顔
・手の動きがスムーズになる
・作業に集中できる
これこそが、私たち変わる介護が目指す
「良くなるケア」の
実践だと実感しました。
▼科学的根拠
実は、この実践には
科学的な裏付けがあります。
認知症の方にとって
・慣れ親しんだ活動が心理的安定をもたらす
・「教える」という役割が自己効力感を高める
・手芸活動が認知機能の維持に効果的
ということが示されています。
また、日本作業療法士協会の
ガイドラインでも、
「その人らしい作業」
の重要性が強調されており、
今回の実践がエビデンスに
基づいたものだと確信しています。
▼今後の展開はコミュニティづくり
1体1の中では作業活動に興味を持ち
実施をしてくれているため、
次のステップを考えています。
・他の利用者様との活動
・複数の利用者様同士でのコミュニティ形成
・施設職員の負担軽減
上記のような目的の元、
リハビリ職ではなくても
実施できる環境づくりを
提供できることを目標にしました。
具体的には
・職員さんが道具の準備
・複数の利用者様が同時に参加可能な環境づくり
・声かけの頻度を減らし、自然な交流を促進
を実施をしていきたいと
考えています。
これにより、利用者様が
自分の得意なことや好きなことを実施でき、
心と体にゆとりが生まれ、
施設全体の負担軽減にも
つながると期待しています。
▼実践から学んだこと
この取り組みを通じて学んだことをまとめます。
1.その人の生活歴を活かす
2.「教わる」から「教える」への転換
3.無理をしないペース設定
好きな活動を行うだけではなく、
安全に過ごしながら
施設全体の負担の軽減を
達成できると考えています。
▼まとめ
今回の編み物・パッチワークという
作業活動を通じて、
利用者様の生活に
大きな変化をもたらすことができました。
今回の実践が、同じような課題を
抱える施設やご家族の
参考になれば幸いです。
それではまた!