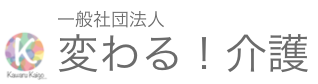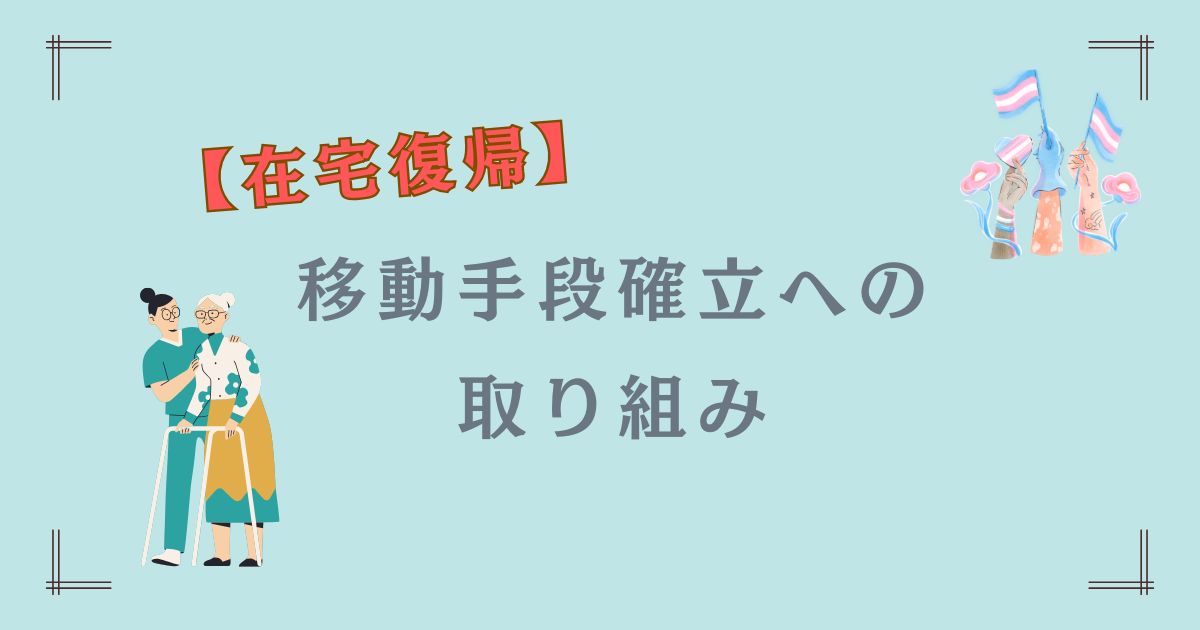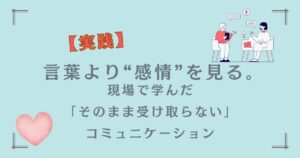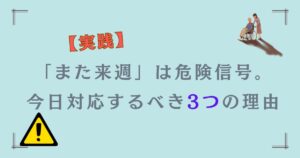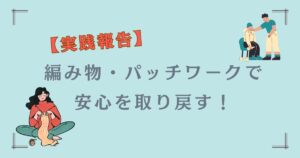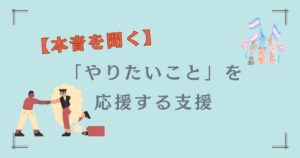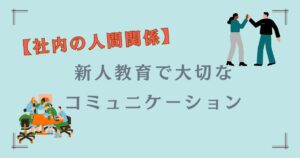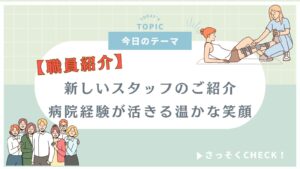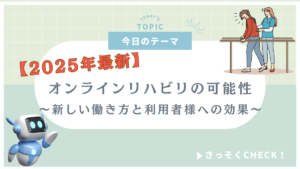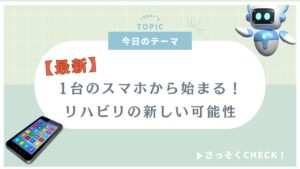みなさん、こんにちは!
変わる介護の岩崎です。
今日のテーマは
【転倒後の在宅復帰~移動手段確立への取り組み~】
です。
今回は、OT2名で担当させて頂いた
転倒後に在宅復帰された方の
ケースについてお話ししたいと思います。
・在宅でのリハビリに関わっている
・転倒予防のアプローチを知りたい
・多職種連携の具体例を学びたい
そんな方におすすめの内容です。
ぜひ最後までご覧ください!
▼入居者様の状況とリハビリの目的
今回担当させて頂いた方は、
転倒後の骨折から復帰された方です。
岩崎を含めてOT2名で、
それぞれ異なる生活機能の視点を
持って担当させて頂きました。
リハビリの主な目的は以下の通りです。
・転倒予防の徹底
・室内移動手段の確立
・トイレまでの移動手段を確保すること
退院後の一番の目的は、
安全に生活していただくことでした。
▼初期の課題
骨折した影響で体力や筋力が落ちてしまい、
歩行器に依存しやすい状態でした。
本人様の中では、
体に以下のような悩みが生じていました。
・肩、肘、首回りに筋肉の張りや痛みが出現
・依存的に歩行器を使っているため、方向転換時に体がふらつく
・転倒の可能性が高い
再度の転倒を予防することが、
重要度が高いと考え以下のような
アプローチを行うことを
チーム間で話しました。
▼具体的な取り組み
最初に取り組んだのは、
移動手段の確立です。
入居者様がもともと使っていた歩行器では
安定感が低く転倒の危険が高いと考え、
体を支えるのに適した
しっかりとしたタイプの歩行器を提案しました。
どんな歩行器にもメリットデメリットがある為、
「どれがよいか」ということを
入居者様と確認しながら試しつつ、
歩行器だけではなく、部屋の中に設置型の手すりを置くことで、
どちらの手段を取ったとしても
安全な移動ができるように話をしました。
▼ケアマネジャーとの連携
ケアマネジャーには体力が落ちて
歩行器の使用が不安定であることを伝えつつ、
しっかりとした歩行器を
提案し取り寄せてもらいました。
そして実際に入居者様にも利用してもらい、
気づいた点や入居者様の言葉をフィードバックしました。
主には、安全性が向上していること、
本人様の受け入れが良かったこと等
ケアマネジャーが知りたいと思う内容を
中心にお伝えました。
▼訪問後の結果
リハビリ回数で言うと
週2回の訪問を4週間続けたところ、
成果が出ました。
結果的に
・しっかりとした歩行器は使わなくても安全に歩けるようになった
・ふらつきの軽減
・廊下を1往復歩いても、首や肩に痛みが出なくなった
改善の理由として考えられるのは、
室内を歩かれていたことにより、
体力が生活の中で徐々に戻ってきたということが
一つの理由だと思います。
▼リハビリの場面と実生活の違い
ここで大切な気づきがありました。
生活の中に運動の機会を取り入れることが、
入居者様の生活をより良くするために
不可欠であるということです。
訪問時には、しっかりとした歩行器を使用することで
歩行が安定し、安心して移動できるようになった
入居者様の様子が見られました。
その様子をケアマネジャーにもお伝えしましたが、
一方で、入居者様ご自身が
その場で本音を話されないこともあるため、
スタッフからの情報を共有してもらえるよう
働きかけました。
実際、体力が向上してくると
「もともと使っていた歩行器を使いたい」
という希望が出てくることもありました。
そのため、運動能力や生活環境をふまえ、
体に合った歩行手段を
柔軟に検討していく必要があります。
こうした関わりを通じて、
入居者様の話に耳を傾けながらも、
チームで多角的に情報を集め、
最適な生活方法を一緒に考え、
運動が自然に生活の中に組み込まれるように
支援していくことの大切さを、
入居者様から学ばせていただきました。
▼今後の方針
現在は安全に移動できるようになったことで、
歩行器については
入居者様の選択を尊重しています。
ただし、手すりについては、
歩行器だけでは不安なので残してあります。
今後、不要であれば撤去するなど、
希望や身体状況に合わせて
進めていきたいと思います。
▼まとめ
今回のケースを通じて学んだことは、
・OT2名での多角的なアプローチの有効性
・ケアマネジャーとの具体的な連携方法
・リハビリ場面と実生活の違いを認識することの重要性
・本人の選択と日常的な実践しやすさを最優先にすること
転倒後の在宅復帰では安全性の確保と
本人の意向のバランスを取りながら、
継続可能な方法を見つけることが
大切だと改めて感じました。
それではまた!